Warning: Undefined array key 4 in /home/kazu5321/kazu5321.com/public_html/wp-content/themes/jstork_custom/functions.php on line 56
Warning: Undefined array key 6 in /home/kazu5321/kazu5321.com/public_html/wp-content/themes/jstork_custom/functions.php on line 61
今回のキーワードは、『神経回路』です。
小さいころに、運動もできて、勉強もできる。なんて人いませんでしたか?
僕の周りにもいました。
運動もできて、頭もいい。
なぜかその人だけ、時間が多くあるように感じる。
それはなぜなんだろう、という疑問を解決するヒントになるかもしれません。
スポンサードサーチ
運動はなぜ大事か。
子供のころ、『外に行って遊んできなさい』ってよく言われませんでしたか?
私は、よく外で遊んでいたので、あまり言われていなかったです。笑
ところが、私の弟は今中学1年生なんですが、ゲームばっかり。
外で遊ぶのはまれです。
スケボーにも少しはまったんですが、1ヵ月ほどで飽き。
柔道もやったんですが、一年たたずにやらなくなってしまいました。
将来が不安、、、
私自身の不安は置いておいて、説明していきます。
運動自体は、いろいろな経験をすることにおいて、意味があると思います。
小さいころから様々なことに触れる。
いろんな体験をする。
刺激のある環境に行く。など、多くの経験が人を成長させてくれます。
刺激があることで、脳が刺激されます。
刺激があると、それに対応する神経回路が作られます。
この神経回路、最初はボロボロのコースなんです。
このコースは、多く使うことで、少しずつ修復されていきます。
修復されつつ、効率的に働くにはどうすれば良いかを考えてくれます。
かってに、効率的にするためにコースを更新してくれるわけです。
この『神経回路』小さい頃には多く作られるんです。
視覚での研究
生後の視覚機能を支える神経回路の発達には生後の正常な視覚体験が必要である/自然科学研究機構 生理学研究所
出典元:生理学研究所
神経回路を構成するのには、刺激が必要というのを、研究で表したもの。
私たち哺乳類の脳の機能は、生まれ育った環境に適応できるように生後の体験や学習に依存して発達します。今回、生理学研究所の石川理子研究員と吉村由美子教授らは、生後の視覚体験を操作したラットを用いて、一次視覚野における神経細胞回路網の発達過程を詳細に調べました。その結果、生後発達期に正常な視覚体験をすると視覚野に微小神経回路網が構築されますが、視覚体験を全く経ない、あるいは形ある物を見ることなく生育したラットの視覚野では、微小神経回路網が形成されないことがわかりました。本研究成果は、正常な脳機能の発達に生後どのような体験が必要となるのかを知る上で重要と考えられます。
出典元:生理学研究所
このように、発達過程で刺激が与えられる事が大事かが示唆されています。
そのため、小さいころに脳への刺激を与えておくことで、それに対応する神経回路が形成されれうわけです。
いろんな経験をしている人は、何かを始めるときでもコツをつかむのが早いですよね。
さらにいろんな経験をすることで、少しの環境変化に驚くことなく対応できます。
環境変化による、体のこわばり、緊張などはパフォーマンスを低下させてしまいますよね。
プロスポーツ選手たちは、大事な時でもパフォーマンスを発揮できるのは、これも関係していると思います。
スポンサードサーチ
勉強とのつながり。
これには、グリア細胞由来神経栄養因子なども関係すると思いますので、今後紹介しようと思います。
勉強も、運動と同じでいろんな経験の蓄積だと思います。
運動をしている人は、新しい刺激に対して、積極的に取り入れようとする傾向にあると思います。
もちろん、『運動バカ』って人もいると思いますが。
これは、完全に興味の影響。
本気を出せば!ってやつですね。
上記にも書いた通りいろんな刺激をうけていると、神経回路が構築されます。
また、脳には他感覚の統合機能にもある通り、機能を補填する機能があります。
得られた情報で、わからないところがあればそれを補ってくれるということです。
これが、『運動神経が良い』とか、『飲み込みが早い』につながるのではないかと思います。
今からじゃ遅いのか。
そんなことはないです!
今からでも始めましょう。
運動によって、脳の血流量の改善が得られる事は研究でも示されています。
また、記憶に新しいのは海馬領域の容量増大の話。
運動で脳容量が増加する:世界の最新健康・栄養ニュース
出典元:リンクデダイエット
冒頭にこんな事が書かれています。
有酸素運動を行うことで記憶機能が改善し、また加齢に伴い低下する脳の健康維持に有益である可能性があると豪州西シドニー大学の研究者らが報告している。
出典元:リンクデダイエット
運動による、神経栄養因子という物質が脳にとても有用なんではないかと指摘しています。
これを出すには有酸素運動が有効です。
ジムに行けない、時間がない。
という人もとりあえず走るだけで、いいんですね。
その効果はとても大きいです。
いきなり、行うのは難しいので少しずつ初めて見るのはどうでしょうか。
無理せず続けていきましょう!
最後までありがとうございました。
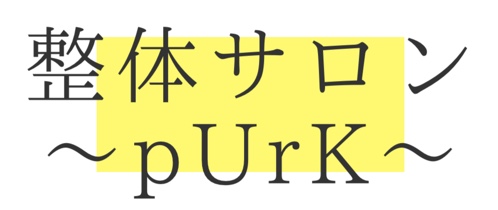



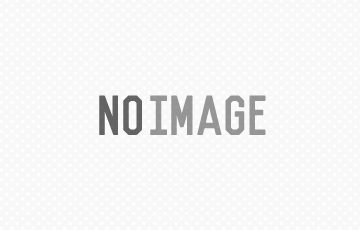











コメントを残す